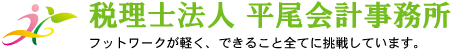起業前にしっかりと研究しておくことは、成功確率を高め、リスクを最小限に抑えるために非常に重要です。以下に「起業の心得と手引き」として、各観点から整理してお伝えします。
- 同業他社の研究
目的:市場の飽和度、差別化のポイント、価格帯、サービス内容などを把握
調査ポイント:地域の競合店(Web・現地視察)
価格・サービス内容・営業時間・口コミの傾向
SNSやブログでの発信内容(顧客との距離感や戦略)
強みと弱み(例:スピード重視か品質重視か)
- 成功者の研究
目的:成功するための「パターン」や「共通点」を見つける
調査ポイント:起業ストーリー(なぜ成功したのか)
強みの活かし方(スキル・人脈・発信力など)
どのような市場戦略・販促を打ったか
顧客との関係性の作り方(リピーター獲得法)
- 失敗者の研究
目的:よくある「落とし穴」を事前に回避するため
調査ポイント:原因:資金ショート、人材トラブル、集客不足、過剰在庫など
最初に見落としたこと(甘い需要予測、準備不足など)
お金の使い方(初期投資に偏りすぎた など)
顧客視点を無視したサービス設計
- マーケティング分析
目的:ターゲット顧客を明確にし、「売れる仕組み」をつくるため
調査ポイント:ターゲット(年齢・性別・職業・ライフスタイル)
競合との違い(ポジショニング)
顧客のニーズ(悩み、望むこと、満足要因)
集客チャネル(Web、SNS、広告、紹介など)
価格戦略(高単価か回転重視か)
- 経営観点からの研究
目的:長く続くビジネスを作るために「仕組み」と「数字」を理解する
調査ポイント:損益計算書(PL)・資金繰り(キャッシュフロー)の基礎
固定費・変動費・損益分岐点の把握
人材管理・育成の仕組み(自分一人で回せるか、人を雇うか)
顧客管理・再来店率の把握(CRM)
サブスクリプションや会員制など継続性の工夫
- 事前許可・申請の観点
目的:法律違反や営業停止にならないために「合法な体制」で始める
チェックポイント:事業内容に応じた許可・届出(例:飲食業、古物商、美容業など)
開業届(税務署)・青色申告承認申請
社会保険・労働保険(従業員がいる場合)
消防署や保健所への確認(物件使用時)
商標登録やドメイン取得の確認(ブランド保護)
起業前の心得(まとめ)
準備8割、本番2割:情報収集と計画立案が成功の鍵
自分の強みを軸にする:他人の真似より自分の価値を活かす
「お客様目線」で考える:自己満足のビジネスは長続きしない
数字と現場の両方を見よ:情熱だけでなく経営感覚も必要
「続ける力」が勝ちを生む:起業は短距離走でなくマラソン
■参考書籍■
【独立希望者必見】面白いほど理解できる(税理士が教える)起業・会社経営Q&A
酒井敏行/松本有史/箕輪俊之/岩木功 箸
TAC株式会社出版事業部 発行
当事務所では、会計ソフトの導入支援を行っています。
会計ソフトで入力なんて不安と思われる方もいらっしゃると思いますが当事務所でしっかりとサポートしますので安心してください。
実際会計ソフトを導入された方のほとんどが、ソフトを導入して良かったとおっしゃっています。
定額減税と確定申告
令和6年度税制改正に伴い、令和6年分所得税について定額による所得税額の特別控除(定額減税)が実施されることとなりました。
定額減税の概要は以下のとおりです。
詳しくは、国税庁の定額減税についてのページをご覧ください。
- 定額減税の対象となる方
定額減税の対象者は、令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下(注)である方)です。
(注) 子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円以下となります。 - 定額減税額(令和6年分特別税額控除の額)
特別控除の額は、次の金額の合計額です。
ただし、その合計額がその人の所得税額を超える場合には、控除される金額は、その所得税額が限度となります。
| 所得税 | 個人住民税 | |
| 本人分 | 3万円 | 1万円 |
| 同一生計配偶者又は扶養親族 | 1人につき3万円 | 1人につき1万円 |
詳しくは、国税庁の定額減税と確定申告ページをご覧ください。
特別控除は、所得の種類によって、次の方法により実施されます。
- 給与所得者に係る特別控除
令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等(賞与を含むものとし、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している勤務先から支払われる給与等に限ります。)につき源泉徴収をされるべき所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」といいます。)の額から特別控除の額に相当する金額が控除されます。これにより控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、以後、令和6年中に支払われる給与等につき源泉徴収されるべき所得税等の額から順次控除されます。
なお、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記載した事項の異動等により、特別控除の額が異動する場合は、年末調整により調整することとなります。
また、次の1~3に該当する場合などは、令和6年分の確定申告において最終的な特別控除の額を計算の上、納付すべき又は還付される所得税の金額を精算することとなります。- 主たる給与の支払者からの給与収入が2,000万円を超えるとき
- 年の途中で退職し、給与等に係る源泉徴収について特別控除の額の控除が行われていない(又は控除しきれない額がある)とき
- 年末調整において、所得税額から特別控除の額を控除した際、控除しきれない額が生じる場合(特別控除の額が所得税額を上回る場合)において、次に該当するとき
- 給与所得以外の所得があるとき
- 退職所得に係る源泉徴収税額があるとき
- 2か所以上から給与の支払を受けているとき
- 公的年金等の受給者に係る特別控除
令和6年6月1日以後最初に厚生労働大臣等から支払われる公的年金等(確定給付企業年金法の規定に基づいて支給を受ける年金等を除きます。)につき源泉徴収をされるべき所得税等の額から特別控除の額に相当する金額が控除されます。これにより控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、以後、令和6年中に支払われる公的年金等につき源泉徴収されるべき所得税等の額から順次控除されます。
なお、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」に記載した事項の異動等により、特別控除の額が異動する場合(例えば、令和6年中に扶養親族の人数が増加した場合など)は、令和6年分の所得税の確定申告(令和7年1月以降)において、最終的な特別控除の額を計算の上、納付すべき又は還付される所得税の金額を精算することとなります。
※給与と公的年金等に係る両方の所得を有する方は、還付申告となる場合や年金所得者に係る申告不要制度(注)の適用がある場合で確定申告をしないときを除き、確定申告において、所得税額から最終的な特別控除の額や源泉徴収税額等を差し引いて納付すべき又は還付される所得税の金額を精算することになります。
(注)年金所得者の申告不要制度…次のいずれにも該当する場合に、計算の結果、納税額がある場合でも、所得税等の確定申告は必要ありません。(注1・2)- 公的年金等の収入金額が400万円以下(注3・4)
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下
(注1)所得税等の確定申告が必要ない場合でも、住民税の申告が必要な場合があります。詳しくは、お住まいの市区町村の窓口にお尋ねください。(注2)所得税等の確定申告が必要ない場合でも、一定の要件に該当する場合には、還付を受けるための申告(還付申告)を行うことで税金が還付されます。
(注3)源泉徴収を要しない公的年金等の規定(所得税法第203条の7)の適用を受けるものを除きます。
(注4)一定の外国年金が国外で支払われる場合などには、源泉徴収の対象となりません。
- 事業所得者等に係る特別控除
原則として、令和6年分の所得税の確定申告(令和7年1月以降)の際に所得税の額から特別控除の額が控除されます。
予定納税の対象となる方については、確定申告での控除を待たずに、令和6年6月以後に通知される、令和6年分の所得税に係る第1期分予定納税額(7月)(注)から本人分に係る特別控除の額に相当する金額が控除されます。
なお、同一生計配偶者または扶養親族に係る特別控除の額に相当する金額については、予定納税額の減額申請の手続により特別控除の額を控除することができ、第1期分予定納税額から控除しきれなかった場合には、控除しきれない部分の金額を第2期分予定納税額(11月)から控除します。
また、確定申告による精算に関する情報は、随時国税庁ホームページにて更新を行っていきます。
(注)特別農業所得者(農業所得の金額に係る一定の要件を満たすものとして申告等をしている方)については、第2期分予定納税額(11月)となります。
お問合せ・ご相談はこちらからどうぞ
 045-869-0337
045-869-0337
営業時間 : 9:30〜18:00《土日祝休日》
吾輩は猫である。名前はまだない。どこで生れたか頓と見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。