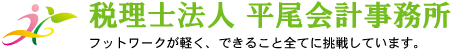起業において、金融機関からの借り入れは最も一般的な資金調達方法です。自己資金だけでは立ち上げ資金や運転資金が不足することも多く、事業を安定的にスタートさせるには外部資金の活用が不可欠です。本記事では、金融機関からの借り入れのメリット・デメリット、そして審査を通すための重要なポイントを税理士の視点で解説します。
- 自己資金に比べて大きな資金を調達できる
- 出資と違い経営権を手放す必要がない
- 利息は経費として計上できる
- 信用力の向上につながる
▼税理士アドバイス:
金融機関からの借り入れは、資金繰りの安定に直結します。利息の支払いは損金算入できるため、税務上も一定のメリットがあります。また、借入実績を積むことで将来的な信用力を高める効果も期待できます。ただし、資金の使途を明確にし、返済計画を現実的に立てることが重要です。返済原資の見込みが曖昧なまま借り入れると、黒字倒産を招くリスクもあります。事業計画書と資金繰り表をセットで用意し、銀行に「返済可能性」を明確に示しましょう。
- 返済義務があり、返済負担が発生する
- 審査に時間と手間がかかる
- 担保や保証人が必要な場合がある
- 資金使途に制限が設けられることがある
▼税理士アドバイス:
借入金は返済義務を伴うため、キャッシュフローの見通しが不十分なまま借り入れるのは危険です。特に創業初期は売上が安定しないため、運転資金を多めに確保しておくことをおすすめします。また、金融機関によって審査基準や融資条件は異なります。複数の金融機関を比較し、創業融資に強い日本政策金融公庫や保証協会付き融資など、条件に合った制度を選ぶことがポイントです。
- 資金使途と返済計画を具体的に示す
- 事業計画書を数値的に整備する
- 自己資金の割合を高めて信用度を上げる
- 税務・会計を正確に管理し信頼性を示す
▼税理士アドバイス:
金融機関は「事業の将来性」と「返済能力」を重視します。そのため、事業計画書には売上・経費・利益・返済原資などを具体的な数字で示すことが大切です。自己資金が多いほど、事業に対する本気度が評価されやすくなります。また、帳簿や申告内容が整っていることは信用を高める要素です。税理士に相談して財務資料を整備することで、融資審査をスムーズに進めることができます。
| 日本政策金融公庫(創業融資) | |
| 主な対象者 | 創業前または創業後概ね2年以内の個人・法人 |
|---|---|
| 融資限度額 | 最大7,200万円(うち運転資金4,800万円) |
| 金利の目安 | 約1.0~2.5%前後(変動) |
| 保証・担保 | 原則無担保・無保証(条件あり) |
| 特徴・ポイント | 審査基準が明確で利用者が多い。自己資金の1/2以上が目安。 |
| 信用保証協会付き融資 | |
| 主な対象者 | 創業1年以内または新規事業を行う中小企業者 |
|---|---|
| 融資限度額 | 地域や制度により上限2,000万円~5,000万円程度 |
| 金利の目安 | 約1.2~2.8%前後(保証料別) |
| 保証・担保 | 保証協会の保証が必要(原則保証料負担あり) |
| 特徴・ポイント | 金融機関+保証協会の二重審査。地方自治体の制度融資と連携可。 |
| 自治体の創業支援融資 | |
| 主な対象者 | 自治体の創業支援認定を受けた個人・法人 |
|---|---|
| 融資限度額 | 自治体により500万円~3,000万円程度 |
| 金利の目安 | 0~2%程度(利子補給・保証料補助あり) |
| 保証・担保 | 保証協会付きが多い |
| 特徴・ポイント | 利子補給や保証料補助があり、実質的な負担が軽い。 |
▼税理士アドバイス:
創業期の資金調達では、まず「日本政策金融公庫」の創業融資を検討するのが一般的です。審査のポイントは、自己資金・事業計画の信頼性・創業者の経歴です。
また、「信用保証協会付き融資」は金融機関との付き合いを構築でき、今後の追加融資にもつながります。
「自治体の創業支援融資」は地域によって条件が異なり、利子補給などの優遇措置があるため、事業所在地の制度を必ず確認しましょう。
税理士としては、借入計画を単なる資金確保と捉えるのではなく、「返済を見据えた資金繰り設計」としてサポートすることが重要です。
■参考書籍■
【独立希望者必見】面白いほど理解できる(税理士が教える)起業・会社経営Q&A
酒井敏行/松本有史/箕輪俊之/岩木功 箸
TAC株式会社出版事業部 発行
当事務所では、会計ソフトの導入支援を行っています。
会計ソフトで入力なんて不安と思われる方もいらっしゃると思いますが当事務所でしっかりとサポートしますので安心してください。
実際会計ソフトを導入された方のほとんどが、ソフトを導入して良かったとおっしゃっています。
定額減税と確定申告
令和6年度税制改正に伴い、令和6年分所得税について定額による所得税額の特別控除(定額減税)が実施されることとなりました。
定額減税の概要は以下のとおりです。
詳しくは、国税庁の定額減税についてのページをご覧ください。
- 定額減税の対象となる方
定額減税の対象者は、令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下(注)である方)です。
(注) 子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円以下となります。 - 定額減税額(令和6年分特別税額控除の額)
特別控除の額は、次の金額の合計額です。
ただし、その合計額がその人の所得税額を超える場合には、控除される金額は、その所得税額が限度となります。
| 所得税 | 個人住民税 | |
| 本人分 | 3万円 | 1万円 |
| 同一生計配偶者又は扶養親族 | 1人につき3万円 | 1人につき1万円 |
詳しくは、国税庁の定額減税と確定申告ページをご覧ください。
特別控除は、所得の種類によって、次の方法により実施されます。
- 給与所得者に係る特別控除
令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等(賞与を含むものとし、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している勤務先から支払われる給与等に限ります。)につき源泉徴収をされるべき所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」といいます。)の額から特別控除の額に相当する金額が控除されます。これにより控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、以後、令和6年中に支払われる給与等につき源泉徴収されるべき所得税等の額から順次控除されます。
なお、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記載した事項の異動等により、特別控除の額が異動する場合は、年末調整により調整することとなります。
また、次の1~3に該当する場合などは、令和6年分の確定申告において最終的な特別控除の額を計算の上、納付すべき又は還付される所得税の金額を精算することとなります。- 主たる給与の支払者からの給与収入が2,000万円を超えるとき
- 年の途中で退職し、給与等に係る源泉徴収について特別控除の額の控除が行われていない(又は控除しきれない額がある)とき
- 年末調整において、所得税額から特別控除の額を控除した際、控除しきれない額が生じる場合(特別控除の額が所得税額を上回る場合)において、次に該当するとき
- 給与所得以外の所得があるとき
- 退職所得に係る源泉徴収税額があるとき
- 2か所以上から給与の支払を受けているとき
- 公的年金等の受給者に係る特別控除
令和6年6月1日以後最初に厚生労働大臣等から支払われる公的年金等(確定給付企業年金法の規定に基づいて支給を受ける年金等を除きます。)につき源泉徴収をされるべき所得税等の額から特別控除の額に相当する金額が控除されます。これにより控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、以後、令和6年中に支払われる公的年金等につき源泉徴収されるべき所得税等の額から順次控除されます。
なお、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」に記載した事項の異動等により、特別控除の額が異動する場合(例えば、令和6年中に扶養親族の人数が増加した場合など)は、令和6年分の所得税の確定申告(令和7年1月以降)において、最終的な特別控除の額を計算の上、納付すべき又は還付される所得税の金額を精算することとなります。
※給与と公的年金等に係る両方の所得を有する方は、還付申告となる場合や年金所得者に係る申告不要制度(注)の適用がある場合で確定申告をしないときを除き、確定申告において、所得税額から最終的な特別控除の額や源泉徴収税額等を差し引いて納付すべき又は還付される所得税の金額を精算することになります。
(注)年金所得者の申告不要制度…次のいずれにも該当する場合に、計算の結果、納税額がある場合でも、所得税等の確定申告は必要ありません。(注1・2)- 公的年金等の収入金額が400万円以下(注3・4)
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下
(注1)所得税等の確定申告が必要ない場合でも、住民税の申告が必要な場合があります。詳しくは、お住まいの市区町村の窓口にお尋ねください。(注2)所得税等の確定申告が必要ない場合でも、一定の要件に該当する場合には、還付を受けるための申告(還付申告)を行うことで税金が還付されます。
(注3)源泉徴収を要しない公的年金等の規定(所得税法第203条の7)の適用を受けるものを除きます。
(注4)一定の外国年金が国外で支払われる場合などには、源泉徴収の対象となりません。
- 事業所得者等に係る特別控除
原則として、令和6年分の所得税の確定申告(令和7年1月以降)の際に所得税の額から特別控除の額が控除されます。
予定納税の対象となる方については、確定申告での控除を待たずに、令和6年6月以後に通知される、令和6年分の所得税に係る第1期分予定納税額(7月)(注)から本人分に係る特別控除の額に相当する金額が控除されます。
なお、同一生計配偶者または扶養親族に係る特別控除の額に相当する金額については、予定納税額の減額申請の手続により特別控除の額を控除することができ、第1期分予定納税額から控除しきれなかった場合には、控除しきれない部分の金額を第2期分予定納税額(11月)から控除します。
また、確定申告による精算に関する情報は、随時国税庁ホームページにて更新を行っていきます。
(注)特別農業所得者(農業所得の金額に係る一定の要件を満たすものとして申告等をしている方)については、第2期分予定納税額(11月)となります。
お問合せ・ご相談はこちらからどうぞ
 045-869-0337
045-869-0337
営業時間 : 9:30〜18:00《土日祝休日》
吾輩は猫である。名前はまだない。どこで生れたか頓と見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。